

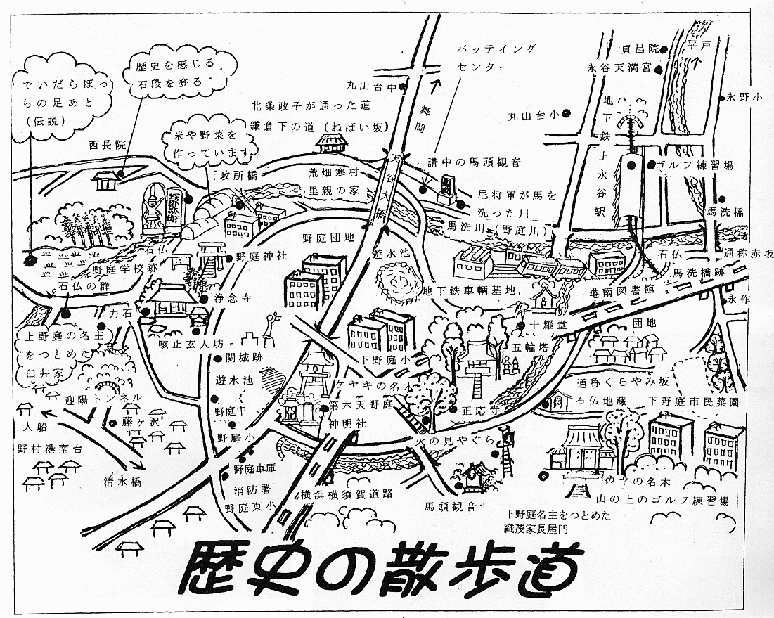 |
| 野庭の今昔 | 昔は,野庭団地用の30万坪の土地にそのころわずか2けんの農家があるだけだった。山林が60 %,田畑が40%で,山はほとんどがぞう木林だった。山にすむけものも多く,タヌキ,キツネ,野ウサギ, キジ,山ドリなどがわがもの顔でとびまわっていたそうだ。 どうして野庭といわれるようになったのかははっきりしないが,野庭の地に人が住み,田畑をつくり始 めたのが1125年のころで,能婆,野葉,または野場と名づけられたようだ。 その後,人が住み着き野庭郷となり,上野庭村,下野庭村,そして野庭町となった。明治6年,上・下 野庭村共同で下野庭村正念寺にかりの校舎をたて,読み書きそろばんの授業が始まった。 明治10年10月に上野庭村(現在の野庭神社の下の竹やぶの所)に校舎を建て,これを野庭学校と いい,本かく的に教育が始められた。明治21年,町村制が出され上・下野庭村と上・下永谷の4つの 村がひとつにまとまり,,永谷の「永」と野庭の「野」をとり,永野村がたん生した。2年後に「小学校は 村の中央におくべし」ということで,現在の永野小の地にたてられた。 野庭学校の校舎は,村役場(永野小のとなり)にうつされた。昭和のはじめには,ふたたび上野庭に, 上野庭公会堂(現在の上野庭町内会館)としてもどった。 |
| 関城あと | 野庭団地一たいはその昔,村のあざ名を深田町といい,この高台を関城あととよんでいた。団地がつ くられる前は畑であったが,ここに関城という城があったといわれている。 野庭川をはさんで北がわのおかに鎌倉古道が通じていた。源頼朝がばくふを開くと同時に奥州方面へ ぬける道として開いた道である。関城はばくふのじゅうしん和田義盛が頼朝の命により鎌倉の北の守り のためにつくられたといわれている。かつては,物見やぐらのあとが残っていた。 |
| 織茂家の長屋門 | 江戸末期に建てられ,名手級の農家であったことをうかがわせるものである。農家の長屋門は門とな や,使用人の住まいをひとつにしたものだが,当時のものはなやと作業場となっていた。 |
| 下野庭神明社 | 下野庭の氏神で,祭神は天照大神である。野庭団地がつくられることになったので,今の場所にうつさ れた。 |
| 浄念寺の力石 | 重さが約70kgの石で,遊び道具の少なかった時代だったので武士や村人たちが力くらべをするため にこの石を使っていたといわれている。 日野に住む若者にもっていかれてしまったこともあったが, |
| せきとめ玄入坊 のほこら |
昔,玄入坊という旅のおぼうさんが上野庭を通りかかり,せきで苦しむ村人をみて「助けてあげよう」と いい,村人にあなをほらせ,病人の身代わりとなって自分が生きうめとなり病人をすくったというでんせつ が残っている。玄入坊は「わたしのおきょうの声が聞こえている間は竹づつから1日3回水を流しこんで もらいたい。」といったという。今でもさんぱいする人がいて,竹づつに湯茶を入れてそなえている。 |
| 迎陽トンネル | 昔,野庭口といわれたこのあたりの道は,曲がりくねっていて坂もきつく,歩くにも馬車で通るのも大変 だった。そこで明治40年ころにトンネルをつくることを村で決めて,村人みんなの手でほってつくられた トンネルである。かんせいしたのは大正4年のことであるから,10年近くもかかったことになる。昭和53 年に横浜市によって現在のようにコンクリートでつくりなおされた。 |
| 野庭神社 | 上野庭の氏神で元亀元年(1570)のかんせいといわれる。祭神はヤマトタケルノミコトである。 |
| 地神塔 | いねなどの農作物のほう作をまつる神で,秋冬は山の神として山を守り,春夏にはさとに下って田畑を 守っていた。土用の丑の日にはお祭りをした。 |
| 庚申塔 | 江戸時代の村人のしんこうの一つに,「庚申の夜にかぎり,人のねむったすきをみて体のなかにいる 三戸という虫がぬけだして神に人の悪事をもらさずつげると,神がその悪事におうじてわざわいをくだす」 というものであった。村人たちは庚申の夜に三戸が体からぬけださないように一ばん中お酒を飲んだり 歌ったりして過ごしたという。庚申は6年に一度めぐってくる。後にこの庚申の日,または庚申年に庚申塔 をたてることが流行した。庚申塔にはさるが描かれているものが多くみられるが,これは「見ざる,言わざ る,聞かざる」のいましめに結びついたものといわれている。 浄念寺から南に500m行ったところにある庚申塔には,「左ぐみやうじへ,右かまくらみち」と書かれて いて,道案内の役目もしていた。 |
| 馬頭観世音 | 昔から馬は交通の役目をはたしたり,農作業などに使ったりと人々の生活とは切っても切れない関係にあった。そこで馬のくようやわざわいがおこらないようにとの願いをこめて,馬頭観世音が建てられた。 |