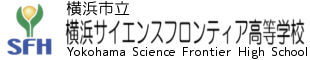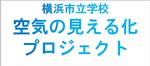校長・常任スーパーアドバイザーあいさつ
ごあいさつ
学校長あいさつ 藤本 貴也(ふじもと たかや)
【インタビュー】横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
常任スーパーアドバイザーあいさつ
浅島誠先生は、平成31年4月1日より和田昭允先生に代わり、常任スーパーアドバイザーに就任していただきました。
 |
議論を通して自己を磨き、大志をもって楽しもう! 浅島 誠(あさしま・まこと) 産業技術総合研究所 名誉フェロー 東京大学 名誉教授 横浜市立大学 名誉教授 帝京大学 学術顧問 特任教授 日本学術振興会 学術顧問
|
令和元年度に和田昭允先生に代わりまして常任スーパーアドバイザーに就任しました浅島です。和田先生は横浜サイエンスフロンティア高校の創設以来、長年名物の「和田サロン」を主宰してきました。その中で和田先生は並々ならぬ情熱を持ち、次世代を担うYSFH の生徒に、科学技術の重要性と科学哲学、人材育成の必要性を述べてきました。YSFH から次世代を担う「サイエンスエリート」を育てたいとの思いが一貫してありました。そこには日本は島国で、これから世界と伍して行くには「科学技術」が重要だと感じていたと思います。和田先生は今では世界中の生命科学の分野では誰でも使っている、DNAの自動解読を世界で初めて取り組まれた卓越した科学者です。それだけに、科学技術の発展がこれからの日本や世界に必ず必要であるとの深い思いからだと思います。先生は単に科学技術の発展だけを考えられたのではなく、若い次世代の生徒に「サイエンス」とは何か、「サイエンスエリート」とは何かと常に問い続けて議論してきました。先生は物理学が専門でしたが、生命科学にも造詣が深く、東大で新しく生物物理学の分野を開拓しました。これからは私も和田先生の「和田イズム」を継承してサロンをしたいと思います。
私が横浜サイエンスフロンティア高校に始めてきたのは、今から約10年前の開校して間もないころでした。当時、高校の名前に「サイエンスフロンティア」が入っていたので自分も大きな驚きとそれ以上にワクワク感と期待感があったことをよく覚えています。横浜サイエンスフロンティア高校は、「サイエンスを本格的に勉強」しようとして看板を掲げた日本で初めての高校です。このオンリーワンでナンバーワンを目指している雰囲気は当時より変わらず現在まで醸し出されています。
サイエンスは物事を良く観察することから始まり、その事象を十分なデータの下に正確に取り出し、自分の頭で考えて、起こっていることの原因と結果を論理的に結び付け、その後、判断や答えを出す知識と智恵のサイクルから生まれます。このサイクルからは新しい創意工夫や叡智、勇気も生まれます。
ところで、サイエンス力を伸ばす方法の一つはお互いが議論することです。日本では議論する雰囲気は少ないように私は感じています。多くの皆さんは自分でよく考えていると思うのですが、それを口に出して議論することが少ないのではないかと思います。これから社会や企業、国際会議等に出ていった時、相手の考えを聞くことも大切ですが、自分の考えをきちんと述べることも大切です。相手に自分の考えを知ってもらい、お互いに尊重しながら、議論することは今後の自己啓発にもとても重要です。お互いを高めるコミュニケーション力です。自分の意見を述べながら相手の意見を聞き、議論を通してお互いがより高い知識や智恵、考えや志や希望に持っていけるのです。お互いの信頼の中での議論は、自分を高めるだけでなく仲間も一緒に更に向上していけるのです。この時、ザックバランに意見を述べあい議論をし、わからないことをトコトン話し合えば新しい見方や考え方を知り、とても有意義な時になります。その議論の過程で自分より優れている仲間の意見を聞いたり、感じたりした時、また自分も頑張ろうとなるのです。「彼はこのように考えているのだ。」「彼も自分と同じように悩んでいるのだ。」「自分の将来の姿はまだ見えないが仲間はどのように考えているのだろうか。」「サイエンスするとはどのようなことだろか。」「成績を上げるにはどうしたらよいのであろうか。」「自分の目標をどのように作り上げれば良いのだろうか。」等、これらは皆さんの多くが常日頃から考えていることであり、また悩んでいることだとも思います。大志に向けて希望を持ち成長させようとする時、色々な問題が出てくるのは当たり前です。その問題を乗り越える勇気と知識と智恵の基盤がサイエンスです。これからは自分の進む道は自分でレールを敷き一つ一つ着実に歩みを続けることです。そのために自分自身を磨くことは一番大切ですが、仲間と議論してお互いが一緒に高い志と希望を持って成長することが出来れば、とても素晴らしいことなのです。
横浜サイエンスフロンティア高校・附属中学校の素晴らしい環境の中で、優れた先生方や先輩、良い仲間に会い、学ぶことの楽しさ、サイエンスをする事の喜びを全身で感じ、大いに学校生活を実りあるものにして下さい。