- (1) 舞台演技の音声の集音
| 舞台で劇などを演じる時に、演技をしている者の声が聞こえにくいというのは、よく経験するところでしょう。音声をどのように集音するかは、出演する人数と一度に舞台に上がる人数によります。少ない人数ならばタイピン型ワイヤレスマイクを使用すると良いでしょう。しかし、この方法ではワイヤレスマイクのチャンネルの数が多くできないという問題と受信機の数や放送機本体の外部入力の数が問題になります。そこで、マイクを何本か立ててステージの音をひろうことになるでしょう。この時、指向性のあまり強くないマイクを使用するのも方法でしょう。マイクを立てる時は、床からの振動をひろってしまうため、マイクスタンドの下に柔らかい布などを敷いておきましょう。または、マイク担当の係を置いて、望遠マイクで集音するのも方法です。マイク係は演技をする人にマイクを向けるので、演技が行われるあらすじをきちんと覚えておかなければなりません。望遠マイクを複数にする時は、集音計画をしっかり立てておきましょう。マイクの本数を増やすと体育館などではハウリングを起こしやすいので、リハーサルをきちんとおこなって、放送機本体のボリュームにマーキングして、一定の音量から上げないようにしましょう。 |
- (2) 映像を撮るときも音声を確保
| 体育祭でも、文化祭の時でも、いえる事ですが、ビデオを録画しておこうとしますと、画面が優先して音がブチブチ切れてしまいます。特に、ビデオ撮影をしているときは、音声記録をきちんととっておくことをお勧めします。編集をした時など、ちょうどよい場面などで音声が途切れてしまうと、おかしなことになります。連続した音が必要なことがあるのですから、劇や運動会の時はテープデッキなど(HiFiビデオなどは長時間の録音が可能なので有効ですが)を音声記録として回しておくと良いでしょう。運動会などは、特に音が途切れることなく流れていることがあり、編集すると特に音がずたずたになります。そんな時、音声記録が別にあると大変番組の制作が楽になる時があります。余裕があればやっておきたいものです。 |
- (3) 舞台のソデでミキシングも
| 演技などの様子をみながら音声のミキシングをするのがあたりまえです。しかし、体育館などのコントロール・ルームからでは舞台全体を見渡すことができない設計の場合が多いようです。この時は、体育祭と同じようなシステムを組んで、舞台のソデで音声のミキシングを行いましょう。ミキサーの外部出力は、ラインで体育館放送機の外部入力に入れます。外部入力に入れるときの注意は、体育祭と同じです。 |
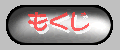
| 
| 
| 
| 
|

| 
|  |