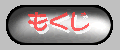
| 
| 
| 
| 
|

| 
|  |
(1)スピーカー
| 体育祭の放送をしようとする時,校庭のスピーカーの位置と,校庭に流れる音の状態をチェックすることが大切です。最近では,学校周辺の住宅から騒音の苦情が出るケースが多く,注意したいものです。しかし,ボリュームを下げていきますと,校庭の中で音が聞こえないデッド・ポイントができます。(ひどい場合は,音量を上げても聞こえにくい場所がありますのでチェックしてみましょう。特に校舎を増設したなどの経験のある学校の場合は,最初の設定と変わっていますので,デッド・ポイントができている可能性が高いのです。) このデッド・ポイントをなくすようにスピーカーの位置を変えたり,増設したりしますとまんべんなく校庭で音が聞こえるようになります。スピーカーを多くして,ボリュームを絞った方が実際の音は小さくなりますが,校庭では良く聞こえるようになる場合が多いのです。 音は反射しますから反射した音を空に逃がしてやったり,工夫する点はありますので専門家に依頼してスピーカーのボリュームを絞っても校庭で音が聞こえる状態を作り出しましょう。そして,この時学校の外にも足を運び,どの程度のボリューム・レベルでどの程度の音が学校の外に漏れているのかも知っておくと良いでしょう。 |
|
スピーカーの音と同様に,ワイヤレスマイクの電波が届かないデッド・ポイントが校庭にある場合も多くあります。放送機本体でワイヤレスマイクを使用できるようにしてワイヤレスマイクを片手に校庭の中を歩いてみましょう。ワイヤレスマイクの電波を拾えない場所があったならば,専門家に相談しましょう。 受信するアンテナの位置や向き・高さで相当違いますし,複数のアンテナを使用することも可能です。上手にワイヤレスマイクの音を拾うことができたなら,体育祭の「応援合戦」や「徒競走のスタート」など力を発揮するはずです。 音を拾う条件は,校庭に人が入った状態でも違いができますので,体育祭当日に使用した時にもチェックするようにしましょう。 ワイヤレスマイクにはタクシーなどの無線が混線する場合があります。ワイヤレスマイクのチャンネルを変更できるようにしておきましょう。特に,ワイヤレスマイクの電波が弱くなっていたりするとデッド・ポイントができる場合もありますので,体育祭の前日までにチェックしておきたいものです。 |
|
体育祭などでは,校庭でミキシングした音声を放送機本体に引き込み,校庭に流します。最近では校庭が見えない放送室などがあり,体育祭の放送は難しくなってきています。学校放送設備では,たいてい校庭に外部入力のジャックがありますので,レピーターやミキサーの出力をこの外部出力端子に接続します。 ミキサーは,入力のチャンネル数が多い方が利用価値があります。体育祭の場合 壇上と壇の下にそれぞれマイクロフォンが必要でしょうし,児童・生徒が実況放送を行うためのテントの中にもマイクが必要ですので,最低でマイクの入力が3チャンネルは必要でしょう。 その他,演技の音楽を手元で操作するためにも,CD,MDプレーヤーやテープデッキも必要ですので,マイクレピーターといえども,外部入力のないレピーターは困ります。音楽を上手につないでいくためには,外部の入力も2チャンネル以上あるほうが望ましいと思えます。さらにワイヤレスマイクの音量の調節もできないと困ります。レピーター自身に受信機がある場合は良いのですが,たいていの場合はついていません。すると,ワイヤレスの受信機の外部出力をレピーターに入力することになりますので,外部入力のチャンネルは最低で3チャンネル必要なことになります。 曲の頭を出す作業が必要になるのも,日常の番組制作と同じです。頭出しがその場でもできるように電池で動くラジカセなどを置いておきましょう。また,まわりがうるさいので,そのラジカセの音が聞こえない場合も考えられますし,近くのマイクに音が入ってしまうことも考えられますから,ヘッドホーンも一緒に持ち 込むと良いでしょう。 |
|
校庭側の入力の端子は雨に濡れないようなボックスを用意することと,端子を引っ張てもすぐにぬけないような端子にするか,コードを一度しばっておくようなフックをつけてもらうと良いでしょう。 また,テントを張ったときに,端子から端子までコードを通すわけですが,コードを踏まれないようにポールを立てるとか,地中にコードを通すとかの工夫をすると良いでしょう。毎年使用する施設ですので,一度しっかりやっておくと大変便利になります。 ホ−ルやボックスがないと窓などを通してコードを校舎に引き込みますが,この時窓を閉められてしまうとコードが挟まれて傷んでしまいます。窓の所を通るコードには窓の部分にウェスや雑巾を巻き付けて,窓で挟まれてもコードが傷まないようにしておきましょう。また,テントからこの端子までの長さのコードは充分な長さのものを用意しておきます。途中でつないだりしますと接触不良をおこしたりして事故の元です。また,断線しやすいものでもありますので,2本用意しておくとよいでしょう。体育祭放送のない体育祭は考えられません。 |
| プログラムの進行にあわせて曲を出せるような工夫をしておきましょう。学年の表示が良いか,競技の表示が良いかなどは,どちらでも良いでしょうが,プログラムに対応してまとめて置いておく場所と整理する箱などを用意しておきましょう。また,駆け足曲などは並足曲と混ざることのないように区別をしておくことが必要です。徒競走の時に並足曲などがかかるなど,みっともない事この上ありません。また,徒競走の時など,曲が途中で終わることなどがありますが,その対応策も考えておく必要があるでしょう。 |
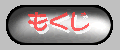
| 
| 
| 
| 
|

| 
|  |